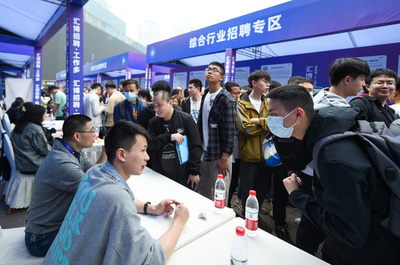中国で尊厳死への関心高まる 深セン市は初の条例施行
このニュースをシェア

【4月24日 東方新報】助かる見込みがなく苦痛を伴う延命治療を拒否し、尊厳死を選ぶ動きが中国で少しずつ広まっている。元気なうちに自分の意志を文書などに記しておく「生前預嘱(リビングウイル)」に注目が高まっている。
南部の広東省(Guangdong)深セン市(Shenzhen)では今年1月1日、改正医療条例が施行され、中国で初めてリビングウイルについての条項が盛り込まれた。医療機関は治癒不可能な終末期の医療措置を行う際、気管挿管や心肺蘇生、生命維持装置の利用などについて患者が事前に表明している意志を尊重するとしている。リビングウイルは、公証人への届け出や2人以上の証人を必要とし、治療にあたる医療関係者は証人に含めない。本人の意志は文書もしくは録音、録画などで示す。
昨年6月に深セン市で改正医療条例が制定されると、7月には女性弁護士の杜(Du)さんがリビングウイル申請第1号となり、公証人に認められた証明書を公開した。「義父が90歳近くで亡くなるまで、私たちは延命治療を希望しましたが、全身に挿管された義父の姿はいたましいものでした」と杜さん。尊厳死に関心を持ち続け、「臨終決定権」を認める深セン市の条例改正を知り、すぐに届け出ることを決めたという。
中国では「死」に関する話題はタブーとされており、日常的に話題になることは少ない。その影響もあってか、末期患者の医療措置は延命措置ばかりが重点に置かれ、緩和ケアのレベルは世界の主要国で遅れていると指摘されている。
民間レベルでは2006年に尊厳死を求める団体が設立され、2013年に北京市リビングウイル普及協会が誕生。深セン市は北京に次いで2021年に普及協会が成立している。北京市リビングウイル普及協会が公開しているリビングウイルのテキスト見本「私の五つの希望書」は5万人が記入している。昨年には87歳の女性翻訳家、沈儀琳(Chen Yilin)さんが末期の腸がんとなり、リビングウイルを提示して延命治療を断り、緩和ケアを受けながら息を引き取った。亡くなる直前、沈さんは「痛みも不快感もない」と語っていた。
中国政府は2017年から全国の一部の病院で緩和ケアを試行的に導入し、ホスピスの建設も進めている。家族が24時間いつでも見舞いができ、家庭的な雰囲気の中、安らかな最後を迎える人も増えている。深セン市の改正条例が制定した際、インターネット上では「尊厳死を支持する」と肯定的意見が多かった。中国でも「死」と向き合う意識が広がりつつある。(c)東方新報/AFPBB New