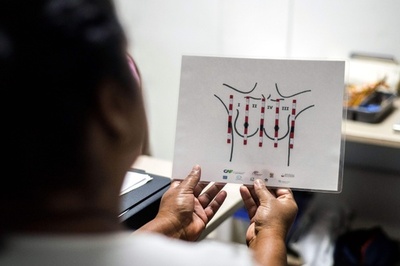反響音で世界を「見る」、エコーロケーション 研究
このニュースをシェア

【3月1日 AFP】コウモリが暗闇の中で進路を定めるために音波を物体に反響させるのと全く同じように、一部の視覚障害者は周囲の状況を把握しながら進むために、自分の口を使ってクリック(舌打ち)音を自然に発しているとの研究論文が2月28日、発表された。認識が困難な物体に「ズームイン」する必要がある場合には、舌打ちの速度と音量を調整するという。
英国王立協会紀要(Proceedings of the Royal Society B)に掲載された論文の共同執筆者で、英ダラム大学(Durham University)のロア・セイラー(Lore Thaler)氏は「人間は自身が出す音を反響させて位置情報を確認する『エコーロケーション(反響定位)』を行えるような『設計』にはなっていないが、視覚障害者はかすかな反響を聞き取ったり、課題の変化に応じて発する音を無意識に調節したりするように、自分の脳を非常にうまく適応させている」と話す。
研究チームは今回の研究で、エコーロケーションの経験を持つ視覚障害者8人を詳細に調査した。
実験では、エコーロケーションに熟達した被験者を雑音が遮断された部屋に入れ、被験者の正面、そして左にそれぞれ45度、90度、135度、180度(真後ろ)とさまざまな位置に木製の円盤を置いた。被験者と円盤との距離は常に1メートルになるようにした。
被験者には、円盤が部屋の中にあるかどうかを判断するために、所定の場所に立って頭を動かさずに自分の口で舌打ち音を発するという課題を与えた。
実験の結果、円盤を0度、45度、90度の角度に置くと、被験者は100%の確率で正解することが分かった。被験者のちょうど左肩越しの位置となる135度に円盤を置くと、正解率が約80%に下がった。真後ろの180度では、正解率は50%だった。
角度が大きく、より難しい位置になるほど、被験者は「舌打ち音を発する回数を増やすとともに、舌打ち音の強度を高める」ことを、研究チームは発見した。
セイラー氏によると、視覚障害者が誰にも教わらずにエコーロケーションを習得する可能性があるという事実は過去の論文でも報告されていたが、まるで音波探知機のように放射音を調節できることを示したのは、今回の研究が初めてだという。
舌打ち音は、舌を口蓋に押しつけて素早く引き下げると、真空状態ができ、これが「弾ける」ことで音が発せされる。この音が空間を伝わり、視覚障害者の周囲にある壁面や物体に反射して、反響音として跳ね返ってくる。
「今回の研究で明らかになったことは、人々にエコーロケーションを指導する際に非常に有用だ」と、セイラー氏は話した。(c)AFP/Mariëtte Le Roux