生まれか育ちか、人は生来暴力的なのか? 研究
このニュースをシェア
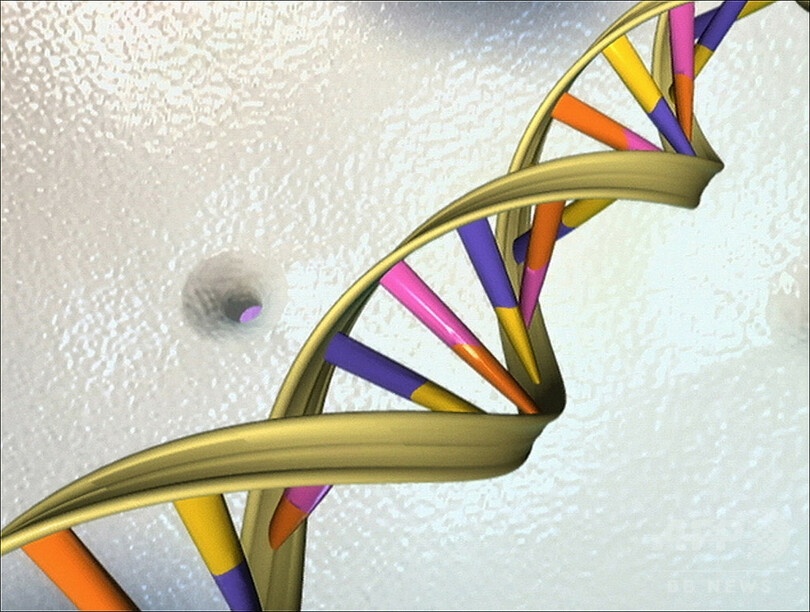
【9月29日 AFP】生まれか育ちか──人が他人をあやめる理由を知るべく探求を続ける哲学者や社会学者、心理学者らの心に何世紀にもわたって居座っているのは、この問いだ。
1650年代に英イングランドのトマス・ホッブス(Thomas Hobbes)が主張したように、人は生来暴力的なのか、それともその1世紀後にジャンジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau)が理論化したように、その振る舞いは育った環境からの影響がより強く反映されるのだろうか。
こうした疑問を進化生物学という新たな角度から再検証した研究論文が27日、英科学誌ネイチャー(Nature)に掲載された。論文を発表したスペインの研究チームは、人の暴力性は、少なくともその一部は祖先から受け継がれたものであり、霊長類に共通するものと結論付けている。
研究では、現存するほ乳類1024種の死に関する400万件以上のデータと、約10万年前~5万年前の旧石器時代(Stone Age)から今日までの人類600人以上のデータを収集し、同生物種の他の個体による致死的暴力が死因となったケースの割合を詳細に調べた。人類の場合では、戦争や殺人事件、幼児殺害、処刑、その他の意図的な殺人による死を対象とした。
研究チームはまた、同じ祖先を持つ生物種間での共通項を調べ、これを基にこれらの祖先の暴力性を推測し、その割合の推移を示すモデルを再構築した。
その結果、同生物種間での殺しは、ほ乳類全体では約0.3%にとどまっていたことが分かった。
このうち、霊長類やげっ歯類、野ウサギに共通の祖先では、同約1.1%となり、その直後に現れた、霊長類とツパイの共通祖先では、その割合が2.3%に上がった。
人類の共通祖先が登場する20万年前~16万年前頃には、その割合は同約2%となった。これは、他の霊長類でも類似のデータが示されているという。
共同執筆者のホセ・マリア・ゴメス・レイエス(Jose Maria Gomez Reyes)氏はAFPに対し、新たなデータは、人類の暴力に進化的な要素があることを示していると述べたが、これらは遺伝のみならず、生存のための環境的圧力の影響を受けている可能性が高いとしている。 (c)AFP/Mariëtte Le Roux








